
巴は文様紋の代表的なものである。本来は、わが国で使用された武具の鞘の形に似ている事から鞘絵となり、のちに水が渦巻いているのに似通っている為、巴の字を当てた。
その為、防火のまじないとされ、平安時代の末期頃から鎧瓦、車輿、衣服の文様に用いられた。
院政が始まった頃、西園寺実季が車の文様に好んで用いたため、次第に権威づけられ以後西園寺家が初めて家紋とする様になった。
武家でも鎌倉時代から東国の諸家が用いていた。
後世にいたり、巴紋が弓矢の神である八幡宮の神紋とみなされるようになり、宇佐八幡宮をはじめ全国各地の八幡宮で使用した為、武士はこれを家紋として神助を受けようとし、菊桐に次いで多く用いられることになった。江戸時代にも人気を博したといわれる。
文様紋だけに種類は極めて広範囲で変化も多い。
「巴紋 まとめ」
- 分類 (文様紋)
- 有名人 (西園寺公望・大石内蔵助・土方歳三・板倉勝重・木下家定)
- 読み仮名 (トモエ)
- 多い名字 (佐藤・山本)

街中の軒瓦 巴紋

左三つ巴
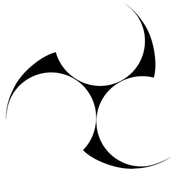
抜け巴


